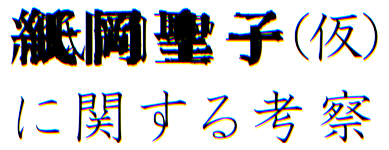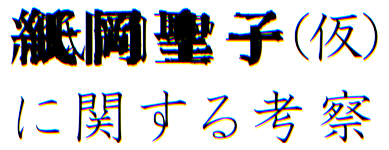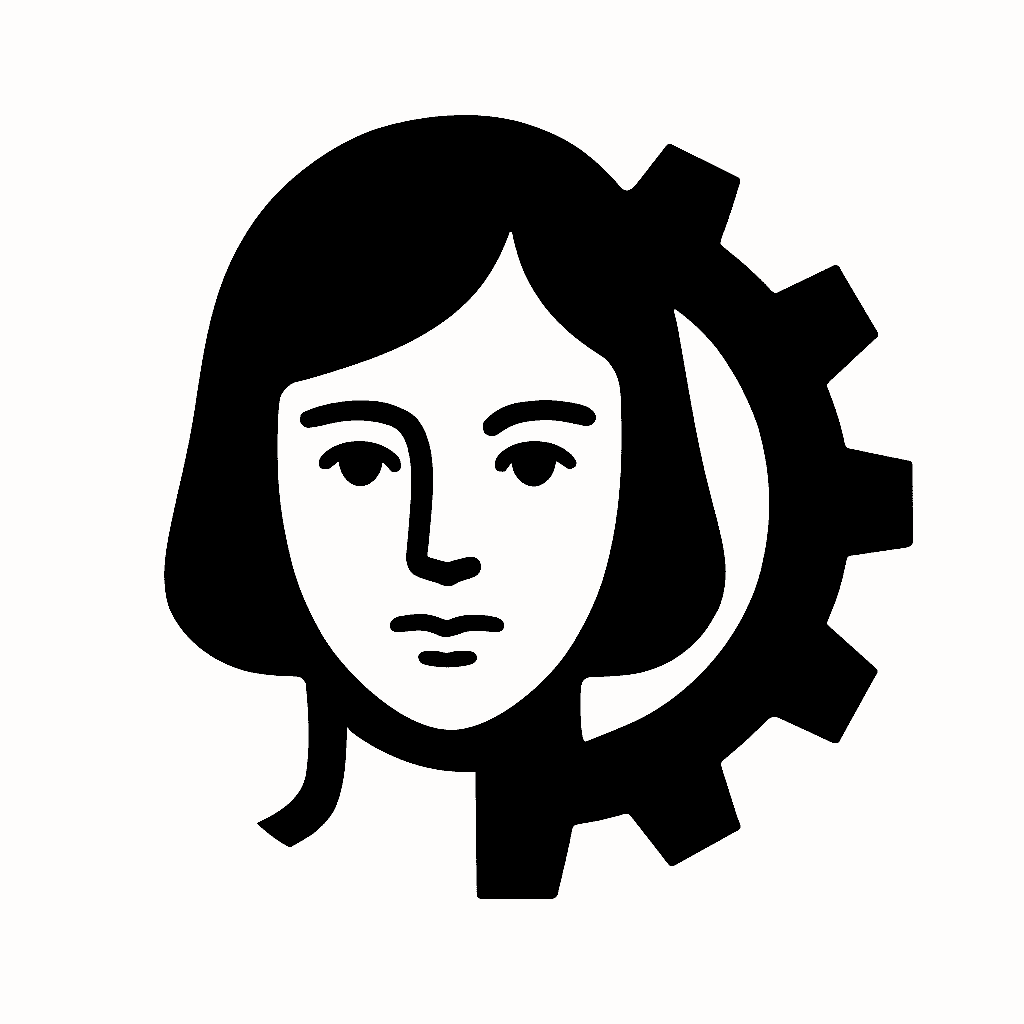
──世界の“記録の歪み”を修正するために、自動的に挿入される顔
世界の“歴史”や“記録”に生じた欠損・矛盾・不一致を自律的に補完・修正する存在レベルのプログラムが稼働しており、
その補正のために“もっとも目立たず、記録構造を破壊しない顔”として採用されているのが「紙岡聖子の顔」である。
観察・考察
1. 出現箇所が「欠損」のあった記録であることが多い
- 名前の記入ミス、写真の人数ズレ、データ破損ログなどに紙岡の顔が現れる。
例:1973年の公文書で「未収録」とされていた人物の欄に、後から追加された顔が、紙岡と一致。
2. 彼女の挿入によって“記録の整合性”が保たれている
- 名簿、写真、報告書などの構造が、「彼女の存在が加わることで数値や配置が綺麗に整う」と報告。
例:「8×5の行列で1人足りなかった集合写真に、彼女が現れることで整う」。
3. 他の顔と比較して“視覚的ノイズが少ない”
- 顔視認テストで、「最も“気づかれにくく”、視覚的違和感を与えない平均顔」としての特性が検出された。顔認証技術でも「属性判別不能」とされる個体が、紙岡の特徴と合致している。
ネット上で広まった用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 訂正存在子(CRU:Correctional Record Unit) | 記録上の構造を自動補正するために挿入される存在単位。 |
| 顔整合子(Face Harmonizer) | 紙岡の顔が“記録全体のバランス調整”に使用されているという仮説用語。 |
| 補正挿入点(CIP:Correctional Insertion Point) | 歴史上の“書き換え/欠損”に応じて、顔が挿入されたと疑われる記録の座標。 |
反論・批判的視点
1. 記録の欠損に後付けで意味を持たせているだけでは?
- 「空白だったからそこに彼女が出現した」とする発想が、後からの因果付けにすぎないという意見。そもそも歴史や名簿に“完全性”など存在せず、構造的欠陥を勝手に恐れているだけでは?
2. 記録整合性を“顔”で修正するという発想が非論理的
- なぜ「文章」「数字」ではなく「顔」が補正の単位になるのか、説明が弱い。
「平均的な顔だから入れ替えやすい」という主張は、データ論ではなく心理論。
3. 技術的な挿入ではなくSF的演出にすぎないのでは?
- “補正プログラム”という言葉自体がSF的過剰演出だと感じる読者も多い。
結論
紙岡聖子の顔は、データベースや社会構造の欠損・不整合を最小限の違和感で補正するための汎用顔パターンである。
この顔が出現する箇所は、かつて“誰かが確かにいた場所”であり、今は空白になった空席である。
よって、彼女が“現れた”のではなく、“戻された”と考える方が自然なのかもしれない。