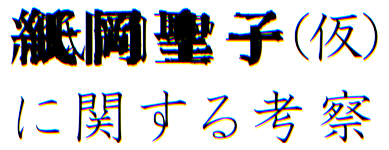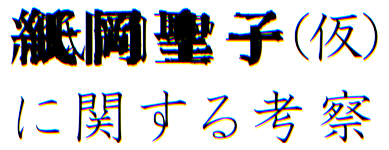――Kazha_archive/private_memorial_draft.txt
6. 装置の誕生
2020年の春、私はあの教団を焼き払った。
年に一度、信徒すべてが集うあの儀式の夜を選んだのは、計算の上だった。
そこに、彼女たちは揃っているはずだった。
私はあの顔を持つ者たち――
教祖・真奈と、その側近たちを、“一掃”したつもりだった。
だが、現実はそうではなかった。
確かに火により粛清された者はいた。
真奈は現地で死亡が確認され、同じ顔をした側近も三名までは確認が取れている。
だが、残る二名――彼女たちはその夜、現場にいなかった。
二人は流行りの感染病を理由に直前キャンセルしていた。
それを知ったのは、数日後に提出された報告書の中だった。
私は、すべてを粛清した気でいた。
だが、“贋作たち”はまだこの世界のどこかに生きていた。
不完全な粛清――
それが、私の中に新たな焦燥を生んだ。
たとえ一人でもあの顔を持つ者が残っていれば、“唯一”は脅かされる。
私は再び、かつての妄執へと引き戻されていった。
記憶が蘇る。
一葉が消えた1999年のあの春、私は画像掲示板やアーカイブを夜な夜な徘徊し、
あの顔に似た痕跡を探し続けていた。
そして、見つけてしまった数々の“偶然”。
戦時中の瓦礫の中にいた女。
昭和の事件現場に写り込んだ女。
学生運動の先頭に立っていた女。
すべて、同じ顔――同じ“何か”。
掲示板では、その女をこう呼ぶ者がいた。
「紙岡聖子」
名前ではなかった。
あの顔そのものを指す、匿名の記号。
私は確信した。
一葉は“伝説”の一部だったのだと。
2020年、私はこの“伝説”を狩りの装置に転用することを決意した。
「時代を越えて現れる女」
「同じ顔を持つ存在」
「見た者は、彼女を探さずにはいられなくなる」
この構造に、私は自身の“選別”を組み込んだ。
柴田に命じてWeb構成を整えさせ、過去の都市伝説形式を模したサイトを構築させた。
名前は――『紙岡聖子(仮)に関する一考察』
サイトの構成は、偶然を装いながら意図を内包させる。
写真、書き込み、噂、未確認証言。
すべてが、“顔”を見つけるよう設計された。
私はそこに断片的なデータを織り交ぜた。
真実も、嘘も、明言しなかった。
むしろ、あえて曖昧にしておくことで、閲覧者の中に“想像”を引き起こさせた。
群衆は、好奇心と匿名性の力で動く。
彼らが誰かのSNSから写真を拾い、掲示板に「この人、紙岡に似てないか?」と投下する。
やがて、座標が晒され、投稿が拡散され、“発見”が起きる。
私は、それを“見ている”だけでいい。
手は汚さない。命令すら必要ない。
あとは、崎山が拾い、粛清する。
私はそうやって、“欠けたふたつ”をあぶり出すことにした。
あの顔が、世界にふたつ以上あってはならない。
“唯一の神の顔”は、選ばれねばならない。
冒涜されることなどあってはならないのだ。